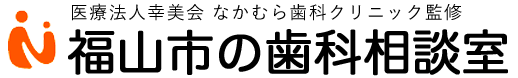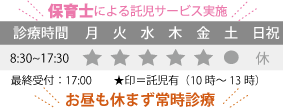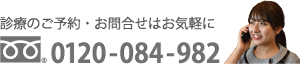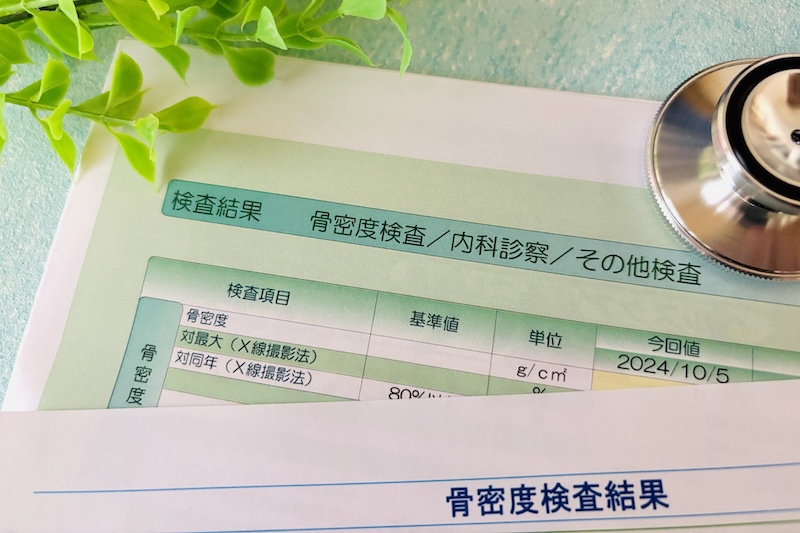歯周病がアルツハイマー型認知症を発症・悪化させる原因?

それだけでも歯周病は十分に恐ろしい病気だと言えますが、歯周病による影響はそれだけに及ばず、全身にも歯周病の原因菌が回って心臓病や脳梗塞、糖尿病をはじめとして多くの病気を引き起こすとも言われています。
そして、高齢者がかかりやすいというイメージの、脳が委縮して認知症を引き起こすアルツハイマー型認知症も歯周病との関係性が指摘されているのです。
今回は、歯周病がアルツハイマー型認知症とどのように関係しているのか、また、認知症を予防するために歯周病をいかに予防していくか、ということについて解説していきます。
1.アルツハイマー型認知症とは
1-1認知症の大多数を占める病気で増加傾向にある
アルツハイマー型認知症は、認知症の中で一番多いタイプのもので、全体の認知症のうちの6~7割を占めると言われています。
現在、アルツハイマー型認知症の人は増える傾向にあり、2025年には65歳以上の20%が認知症にかかってしまうとも予想されています。
1-2脳に異常なタンパク質が溜まって萎縮を起こす
アルツハイマー型認知症は、脳の内部に異常なタンパク質であるアミロイドβ(ベータ)が蓄積することで脳の神経細胞を破壊し、脳がだんだんと委縮していく病気とされています。
脳の萎縮はゆっくりと進行し、物事の認識、記憶、判断といった機能に障害が起こって社会生活において支障をきたしてしまうようになります。
1-3アルツハイマー型認知症で起こる症状
アルツハイマー型認知症になると、次のような症状が起こってきます。
・少し前の記憶がなくなる
・新しいことを覚えられなくなる
・時間や場所がわからなくなってくる
・季節の感覚が薄れる
・人の顔や物が区別できなくなってくる
・理解力・判断力が衰える
・言語障害が起きてくる
・家事や仕事がこなせなくなってくる
・食事、風呂、着替えといった日常生活がおぼつかなくなってくる
・物盗られ妄想が出てくる
・外へ出てうろうろ徘徊する
さらに病状が悪化すると寝たきりの状態になってしまい、数年で死に至るという経過をたどることもあります。
2.歯周病が認知症の発症リスクを高める?

近年の研究によると、歯周病が認知症の発症リスクを高めるということが分かってきています。歯周病は口の中の病気ですが、歯茎の出血によってできた血管の破れた部分から歯周病菌が入りこみ、全身にまわるので、脳にも影響が行く可能性は十分にあります。
歯周病は日本においても世界においても、最もかかっている人が多い生活習慣病であり、日本においては成人の8割もの人がかかっているとも言われています。
ということは、ほとんどの人にとって、アルツハイマー型認知症にかかるリスクはあるということになり、決して他人ごとではないと言えるでしょう。
3.歯周病と認知症の関係性について
歯周病と認知症の関係性について詳しく見ていきましょう。
アルツハイマー型認知症は、脳の内部に異常タンパク質「アミロイドβ」が蓄積することで起こるとされていますが、実はこの異常タンパクは歯周病とも深い関連があることが分かっています。
3-1歯周病にかかるとアミロイドβが増える
歯周病にかかるとアミロイドβが増えることが分かってきています。
歯周病にかかって歯茎から出血すると、その部分から血管内に歯周病菌や歯周病菌が出す毒素が入りこみます。
そして全身にまわって脳内に達すると、そこで炎症性物質が増え、この炎症性物質がアミロイドβを増加させて脳に蓄積していきます。
そうするうちにやがて脳の神経細胞が破壊され、脳が委縮してアルツハイマー型認知症を発症してしまいます。
ちなみに、脳にアミロイドβが蓄積し始めてから認知症の症状が出るまでには、だいたい25年くらいかかることがわかっています。
3-2歯がなくなってしまうことでも認知症リスクが上がる
また、歯周病にかかってあまり噛めなくなることで物理的に脳に刺激がいかなくなることも、認知症のリスクを高める一因になります。
歯周病が進むと歯を失ったり、歯がグラグラになったりしてしっかりと噛むことができなくなります。そうすると必然的にあまり噛まなくて済むようなやわらかいものばかり食べるようになります。
しかしその状態が続くと、脳に噛む刺激が伝わらなくなるので脳が委縮し、認知症が起こりやすくなると言われているのです。
実際にこのことはマウスの実験によっても証明されています。
歯を抜いて流動食だけを与えたマウスは、脳の記憶をつかさどる海馬の神経細胞が減り、認知症になるということが分かっているのです。
4.認知症を防ぐためにも歯周病を予防しよう!

上記でご説明したように、認知症と歯周病には深い関連性があります。
つまり、歯周病を予防することで認知症のリスクを下げられる可能性があります。
認知症を防ぐために、次のような対策をして歯周病を予防、もしくは悪化させないようにしていきましょう。
4-1一番大事なのは毎日のケア
歯周病の主な原因は歯の周囲に溜まった歯垢です。
歯垢が溜まらないようにするためには、最低でも1日に2回は歯磨きをし、清潔な状態を保つことが大事です。
4-2定期的にクリーニングを受けましょう
歯磨きを丁寧にやっていても、歯ブラシが行き届かないところというのは出てきてしまいます。そのような場所には歯垢が蓄積してやがては歯石となり、歯周病を引き起こしたり悪化させたりする原因になります。
そのため、定期的に歯科でクリーニングを受け、歯垢や歯石を溜めこまないようにすることが大事です。
4-3タバコは控えましょう
タバコを吸うと歯周病のリスクは5倍以上にも跳ね上がると言われています。
これまで吸っていた人でも禁煙することでリスクを下げることができますので、現在喫煙している方は徐々にタバコの本数を減らし、最終的には禁煙することをおすすめします。
4-4糖分の摂り過ぎに注意しましょう
糖分は歯垢ができる元になり、摂取する量が多いほど歯垢が溜まって歯周病のリスクを高めます。そのため、糖分の摂り過ぎにも気を付けることが大事です。
4-5全身の健康にも注意を払いましょう
糖尿病や骨粗しょう症の人は歯周病が悪化しやすい傾向があります。つまり、歯周病のリスクを下げるためには、そういった病気にかからないように、バランスの良い食事や生活習慣を改善することも大事です。
5.まとめ
歯周病は認知症、とくにアルツハイマー型認知症との関係が深いので、歯周病予防をしていくことは認知症予防の観点でも重要だということがお分かりになったかと思います。
認知症は一般的に、70歳前後で発症する人が多いですが、脳にアミロイドβが蓄積し始めてから認知症を発症するまでにだいたい25年かかることを考えると、遅くとも40代半ばくらいまでには対策を取っておきたいところです。
アルツハイマー型認知症の原因は不明な部分もありますが、歯周病の対策をできるだけ早くから始めておくことによって少しでもリスクを減らすことができますし、同時に他の全身疾患のリスクを下げることにもつながるので、早くから取り組んでおくに越したことはないでしょう。
ぜひ皆さんも、お口の健康のため、全身の健康のためにも、歯周病対策を始めてみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!