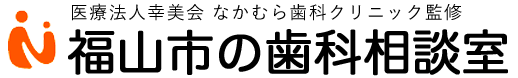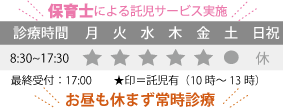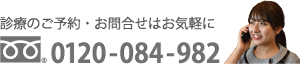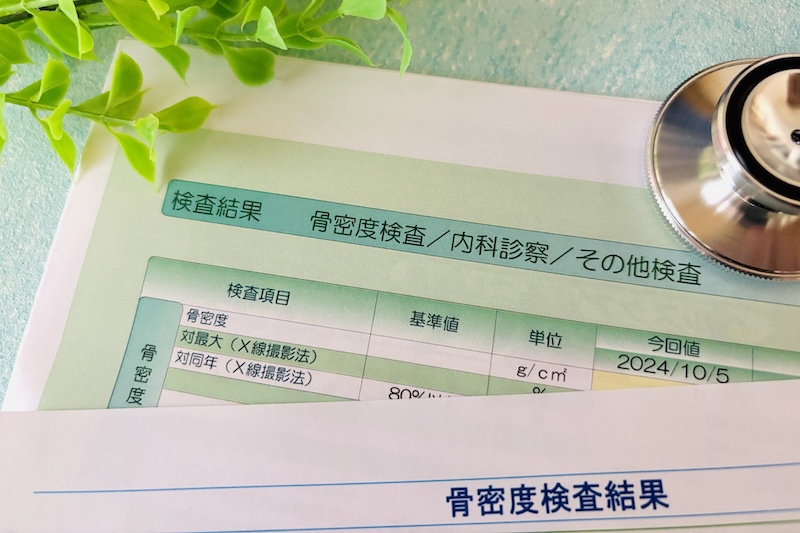歯周病と肺炎の関係性、歯周病が命の危険をもたらす?

歯周病のことをただ歯茎が腫れる、歯茎から血が出るだけの病気だと思っている人もいるかもしれません。
ですが、歯周病は進行性の病気で、病状が悪化すると歯を支える骨も溶かしてしまい、しまいには歯を失ってしまう恐ろしい病気です。
これだけでも十分に恐ろしいのですが、歯周病は全身にもさまざまな害を及ぼすことが明らかになってきています。
その一つが「肺炎」。
肺炎は命の危険を起こすことのある重大な疾患です。
今回は歯周病と肺炎の深い関係性についてご紹介し、どんな人が特に注意が必要なのか、そして予防法などについても解説していきます。
1.歯周病と肺炎の関係性について
口の中の病気である歯周病と肺になぜ関係があるのだろう?と思ってしまいますよね。
実際に歯周病にかかっている人が皆、それによって肺炎を起こしているわけではありません。
歯周病が肺炎を起こす背景には次のようなことが関係しています。
1-1口の中のものが誤って気道に入る「誤嚥性肺炎」
通常であれば、口の中の唾液や食べ物は食道の方に流れていき、肺などの呼吸器がある気道の方には流れていかないようになっています。
仮に誤嚥をしてしまった場合、つまり口の中のものが気道の方に行ってしまった場合、体に備わっている反射機能により咳が出てきちんと排出されるようになっています。
ところが、この機能が何らかの原因で正常に働かなくなってしまうと、口の中のものが気道に入っても反射機能が起こらずに排出されず、肺に達して肺炎を起こしてしまうことがあります。
このような誤嚥による肺炎を「誤嚥性肺炎」と呼びます。
1-2歯周病菌は唾液や飲食物とともに気道に入りこむ
誤嚥性肺炎の原因として歯周病菌が大きく関係していることが、最近の研究によって明らかになってきています。
歯周病菌はお口の中に誰もが持っている細菌で、少数であれば特に問題を起こしませんが、ケア不足が原因で歯と歯茎の溝のところで繁殖すると歯周病を発症させます。
これらの細菌が唾液や飲食物と一緒に気道の方に入っていくことで肺炎のリスクを大きく高めてしまうのです。
2.歯周病が命の危険をもたらす

2-1歯周病が関わる重大な病気
歯周病は誤嚥性肺炎のほかにも、命に関わるさまざまな病気を引き起こすことが問題になっています。
歯周病との関連性が指摘されている重大な病気としては、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、糖尿病、胃がん、アルツハイマー型認知症といったものが代表的です。
つまり、歯周病はもはやお口の中だけの病気ではない、ということであり、このような病気のリスクを高めないためにも歯周病に対するケアが重要になってきます。
2-2誤嚥性肺炎で起こる症状
「肺炎」というと、咳や高熱が続く、というイメージがあるかもしれませんが、誤嚥性肺炎の場合、そのような症状を必ずしも出さないため、肺炎になっていることに気づかれず、発見が遅れることがあります。
発見が遅れると重症化し、命に関わることもあるので、次のような症状がある場合には医師の診察を受けることが大事です。
◆食欲がない
初期症状で現れやすいものとして、食欲不振があります。倦怠感がひどく、元気がない状態が続く場合、注意が必要です。
◆痰が絡むような咳が出る
喉からゴロゴロと音がし、痰が絡むような咳が出る場合も要注意です。これは、誤嚥をしたことで肺に感染症が発生する結果起こります。
◆食べた後にガラガラ声になる
食事をとった後にガラガラ声になるのも誤嚥性肺炎でよく起こる兆候の一つです。
これは、食べ物や飲み物が気管の方に入ってしまうことで声帯を刺激してしまうことで起こります。
◆長く続く微熱
通常の肺炎では高熱が出ることが多いですが、誤嚥性肺炎の場合は微熱が続くことが多いので、体温も日頃からチェックしておくようにしましょう。
3.誤嚥性肺炎はどの年齢でもなるもの?
誤嚥性肺炎は、一般的には体の反射機能が衰えてきた高齢者がかかりやすく、特に注意が必要になります。
高齢に達していない場合には、特に健康状態に問題がなければ誤嚥性肺炎を起こすことは通常はありませんが、脳卒中を起こした方、嚥下機能が衰えてしまっている方、認知症の方、要介護の状態にある方、もしくは免疫力が落ちてしまっている方などにおいては誤嚥性肺炎を起こすことがあるため、注意が必要です。
4.肺炎を予防する方法はあるの?

誤嚥性肺炎を予防する方法としては
・歯周病菌を減らす
・誤嚥自体を起こりにくくする
といった取り組みが効果的です。
一つずつ見ていきましょう。
4-1歯周病菌を減らす
お口の中に歯周病菌が多いと、それだけ誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。
歯周病菌を減らすためには、お口を清潔に保ち、歯周病菌を少なくしておくことが必要不可欠です。
そのためには、まず日頃から食後の歯磨きを丁寧に行うようにしましょう。要介護の状態で、自分で歯みがきが難しい場合には介護する方が磨いてあげるようにしましょう。
なお、高齢者の場合には入れ歯が入っていることが多いため、入れ歯の清掃も忘れずに行うようにしましょう。
また、定期的に歯科医院でクリーニングを受ける、通院が難しい場合には訪問診療サービスを受ける、介護する方が歯科医師や歯科衛生士に正しい口腔ケアの仕方を聞いて正しいケアをおこなう、といったことも大事です。
4-2誤嚥を起こりにくくする
誤嚥を起こりにくくするためには、食事の内容・仕方を工夫する、口の筋力をつける、といったことが効果的です
◆食事の内容・仕方を工夫する
液体のものは喉に一気に流れてしまい誤嚥しやすいため、とろみをつけたりゼリー状にしたりするとよいでしょう。
その際、一度にたくさん口に入れず、少しずつ小分けにして、ゆっくり食べるようにしましょう。
また、食べた後にすぐに横になるのは避け、しばらくは上体を起こしておくようにしましょう。
◆口の筋肉トレーニングをする
根本的な方法として、衰えた口や舌の筋力を鍛えるのはぜひおすすめです。
身近なものを使ってすぐに始められる簡単な方法をご紹介しますので、ぜひ試してみてください。
少し疲れたな、というところまでやってみる、ということを続けているとどんどん筋力がついていくでしょう。
・唇の筋力をつけるトレーニング
唇の筋力を鍛えることにより口を閉じる力を強化します。
準備するものは直径2.5センチくらいのボタンと切れにくい糸のみです。
<方法>
1.ボタンの穴2か所に糸をボタンに通した後、20センチくらい離れたところで両端を結んで輪っかを作る
2.ボタンを唇と歯の間に入れ、しっかりと唇を閉じる。(ボタンを噛まない)
3.糸を引っ張り、唇をしっかり閉じてボタンが出てこないようにする
このステップを10秒くらいかけてゆっくり行います。1日10回くらいが目安です。
・舌の筋力をつけるトレーニング
このトレーニングで使うのはスプーンだけ。
スプーンで舌を押し、それを舌で押し返します。これを10秒間くらい続けてみましょう。
いろいろな方向から押して押し返す、というのも良いです。
これも、1日に10回くらいを目指してやってみましょう。
5.まとめ
誤嚥性肺炎は高齢者の死因のトップを占める重大な病気ですが、この発症に歯周病菌が深く関わっている事実があるということを考えると、歯周病ケアの大切さがお分かりになることでしょう。
歯周病が悪化する最大の原因はお口のケア不足ですので、今からでもお口のケアをしっかりと行うことが誤嚥性肺炎をはじめ、他の重大な病気の予防にもつながっていくということが言えます。
ですが、体の不自由な高齢者や要介護者は自身で清掃をきちんと行えないことが多いため、周囲の人のサポートが大事になってきます。
身近に要介護の人がいて、お口のケアをどうしたらいいのか分からない、という方は歯科医院でいろいろとアドバイスを受けられますので、問い合わせてみることをおすすめします。
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!