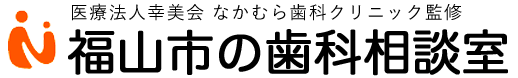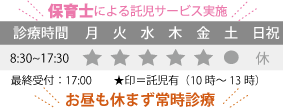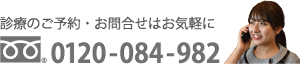歯周病と脳疾患は関係があるの?

ですが近年、歯周病は単に歯の周囲の病気というだけではなく、遠く離れた臓器にも影響してさまざまな病気を起こすことが分かってきていました。
歯周病は時に、脳にも影響を及ぼすことがあります。脳は体を正常に機能させるための司令塔となるところですので、この部分が侵されると、それまで通りの日常生活が送れなくなったり、ひどい場合には生命を脅かしたりすることもあります。
また逆に、脳疾患にかかると歯周病にかかりやすくなるという逆の関係もあります。
今回は、
・歯周病と脳疾患との関係について
・具体的に歯周病がどのような脳疾患を引き起こすのか
・歯周病や脳疾患を予防するにはどうしたらいいか
ということについて解説していきます。
1.歯周病と脳疾患の関係性
歯周病を発症している人はそうでない人と比べて脳疾患のリスクが2.8倍も高くなると言われています。また、逆に脳疾患のある人は歯周病を発症しやすくなります。
それぞれが影響を及ぼし合うメカニズムについて見ていきましょう。
1-1歯周病菌が血管に異変を起こす
◆動脈硬化を起こしてしまう
歯周病によって歯茎に炎症が起こると、歯茎から出血しやすくなります。そうすると、出血部分から歯周病菌や歯周病菌の出す炎症物質が血管の内部に入り込み、全身にまわっていきます。
歯周病菌の出す炎症性物質は、血管の内壁にくっつき、だんだんと蓄積してプラークと呼ばれる構造物をつくっていきます。そしてそれがいずれ厚みを増し、結果的に血管が狭くなっていきます。これは動脈硬化と呼ばれる状態です。
動脈硬化の状態になると、血液の通り道が狭くなるので、血流が途絶えやすくなります。また、そのような状態においてプラークが剥がれると、血の塊ができて血管を詰まらせてしまいます。
このようなことが脳の血管で起こることもありますし、心臓や頸動脈など別の場所から血栓が飛んできて脳の血管で詰まることもあります。
◆脳内に異常タンパクが蓄積してしまう
歯周病菌が作り出す炎症性物質が血液に乗って脳に到達すると、脳内で異常なタンパクが作られて蓄積し、脳の神経細胞にダメージを与えて死滅させ、脳が委縮していくことが分かっています。
1-2歯周病で噛めなくなり、脳に刺激が行かなくなる
歯周病が進行すると、骨がだんだんと溶かされていきますので、しまいには骨が歯を支えきれなくなり、噛むと歯が動いてものが噛みづらくなったり、痛みを感じて固形物を噛めなくなったり、といったことが起こるようになります。
そうすると、必然的にあまり噛まずに済むやわらかいものばかり食べるようになり、噛む刺激が脳に伝わりにくくなることで脳の機能が低下しやすくなると言われています。
1-3脳のダメージによる運動障害で起こる影響
脳の病気により手が不自由になると歯磨きをうまく行うことができず、歯に汚れが蓄積しやすくなります。唇や舌の動きの運動障害が起こると、食べかすが溜まりやすくなり、同様に歯に汚れが溜まりやすくなります。
その結果、歯周病が発症・悪化しやすくなります。
また、脳のダメージの部位によっては嚥下障害でものをうまく飲み込めなくなることがあり、食事の内容が偏ることにより免疫が低下しやすくなります。そしてさらに、やわらかく歯に残りやすい食事ばかりとることも相まって歯周病のリスクが高まります。
2歯周病が影響する脳疾患はどんな病気があるの?

脳疾患と言っても色々な病気がありますが、歯周病が影響する脳疾患としては次のようなものが挙げられます。
2-1脳梗塞
脳梗塞とは、脳内の血管が詰まってしまい、血液が流れなくなることによって栄養や酸素を送ることができなくなり、脳細胞が壊死を起こしてしまう病気です。
脳の細胞は再生しませんので、いったんダメージを受けてしまうと、麻痺やしびれなどの神経症状を起こしたり、そのまま命を落としてしまうこともあります。
また、命を取り留めたとしても言語障害や手足の運動障害などの後遺症が残り、不自由な生活を余儀なくされてしまい、寝たきりや要介護になる可能性が高くなります。
実際に高齢者が寝たきりになる原因の多くを占めるのが脳梗塞だと言われています。
<歯周病との関連>
歯周病菌が出す炎症物質が血管内部に蓄積して血管を細くし、また、血栓を作ることにより血管が詰まって脳梗塞を起こすことがあるとされています。
2-2認知症
認知症の中でも多いアルツハイマー型認知症はだんだんと脳の海馬を中心とした部分が委縮していき、脳の神経細胞が死滅していく病気です。
認知症というと高齢者がかかるもの、と思われがちですが、とくにアルツハイマー型認知症の場合は中年以降の若年者でも発症することがあり、いったん発症すると記憶障害、判断能力の低下、もの盗られ妄想、幻覚、徘徊といった症状が現れます。
<歯周病との関連>
歯周病菌の出す炎症物質が血管に乗って脳に行くと、そこで異常タンパクが作られて神経細胞にダメージを与え、アルツハイマー型認知症を起こしやすくすると言われています。
また、歯周病によってものが噛みにくくなることでやわらかいものばかりを食べるようになり、噛む刺激が脳に伝わらなくなると、認知症につながる可能性があると考えられています。
3.歯周病・脳疾患を予防する方法は?

歯周病を予防することで、脳疾患だけでなく全身のさまざまな病気を予防することにもつながります。また、脳疾患を予防することで歯周病のリスクを下げることができます。
このように、両方の病気の予防をすることで、相乗効果でより高い予防効果が期待できます。それぞれの予防法について見ていきましょう。
3-1歯周病を予防する方法
歯周病の主な原因は歯の周囲に溜まる汚れですので、まずはこれが溜まらないように毎日の歯磨きを丁寧に行うようにしましょう。ただし、磨き残しが蓄積すると歯周病発症のリスクがあるので、定期的に歯科でプロによるクリーニングを受けることも大事です。
また、糖質は歯周病を引き起こしやすくするので、摂りすぎないように注意し、タバコも歯周病リスクを高めるのでなるべく控えるようにしましょう。
3-2脳疾患を予防する方法
◆脳梗塞に関して
脳梗塞を引き起こすリスク要因としては、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、飲酒、過度のストレスといったことが知られています。
このようなリスクを避けるためには、食生活や生活習慣を見直し、健康的でストレスを溜めない生活を送ることが大事です。
◆認知症に関して
認知症を予防するには、しっかりと噛める状態にして脳に刺激を与えることが大事だとよく言われます。そのためは歯のメンテナンスをしっかりと行い、噛める状態を維持するようにしましょう。
アルツハイマー型認知症に関しては完全な予防法は見つかっていませんが、生活習慣病を予防すること、適度な運動をすること、適度な睡眠をとること、過剰なストレスを避けること、楽しく喜びを感じる生活を送ること、といったことが予防につながると言われています。
4.まとめ
今回は歯周病と脳疾患との深い関連についてご紹介しました。脳は他の多くの臓器と違い、一度ダメージを受けると再生することがありません。
そのため、病気を発症してしまうと元通りの治癒が難しく、後遺症や寝たきりにつながることが多くあります。
口内ケアに力を入れて歯周病を予防、改善していくことにより脳疾患のリスクを下げることができますので、ぜひ皆さんも今日からでも意識して取り組んでみてください。
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!