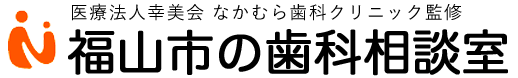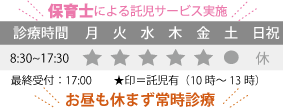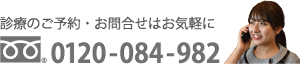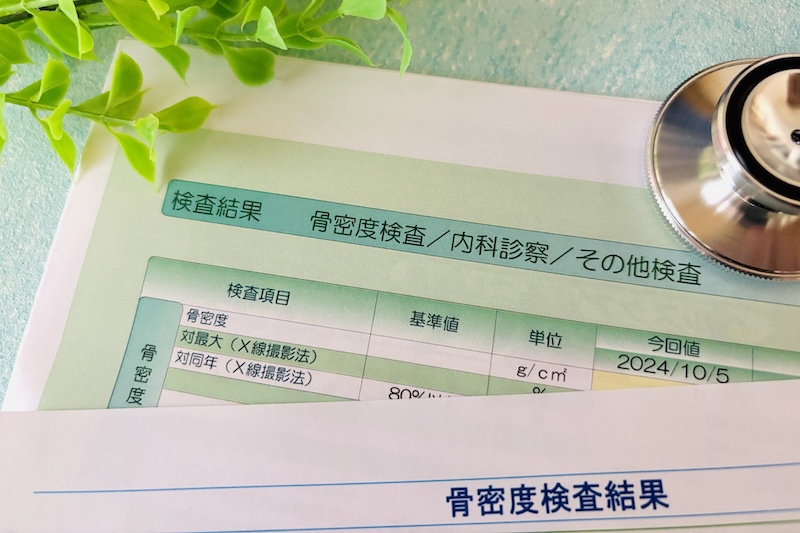歯周病とメタボリックシンドロームの関係性

太っていたり、お腹が出ていたりしていると「メタボだ」、などと言ってしまうように、私たちにとって身近な言葉になっています。
実際は「太っている=メタボ」というわけではないのですが、メタボリックシンドロームと診断されるにはいくつかの基準があり、健康診断で指摘を受ける人も少なくありません。
メタボリックシンドロームはただ太っているという見た目の問題だけではなく、放置していると重大な病気を招く原因となるため注意が必要です。ですがそれだけではなく、実は歯周病とも相互に関係していることが分かっており、その関係性を知って対策していくと、歯周病もメタボリックシンドロームも改善できる可能性があります。
今回は歯周病とメタボリックシンドロームの関係性とそれぞれの対策などについて詳しくご紹介していきます。
1.メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームとは、生活習慣病の前段階の状態ともいえるもので、内臓脂肪が過剰に蓄積されている状態にプラスして、高血圧、空腹時の高血糖、脂質の異常値などがみられる状態のことをいいます。
メタボリックシンドロームはまだ病気と呼べる段階ではありませんが、いずれ糖尿病や動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞といった病気につながる恐れがあるので注意が必要です。
近年は、カロリーオーバーの食事に加えて車社会、デスクワークの人が増え、運動不足気味の人が多いことから、メタボリックシンドロームの状態になっている人が増えています。
2.歯周病とメタボリックシンドロームの関係とは?

歯周病とメタボリックシンドロームは、一方向だけでなく、お互いに影響を与え合う関係性があります。詳しく見ていきましょう。
2-1歯周病がメタボリックシンドロームを引き起こしやすくする
◆ものが食べにくくなることによる影響
歯周病が進行すると、歯がぐらぐらになって物が噛みにくくなったり、さらに重症化すると歯が抜け落ちたりして、ものが噛みにくくなっていきます。
ものが噛みにくいと必然的に高カロリーでやわらかいご飯やパン、麺類などといったものばかり食べるようになります。そのようなものは糖質を多く含んでいますので、血糖値が上がりやすくなり、インシュリンがたくさん分泌されるようになります。
インシュリンにはブドウ糖を中性脂肪に作り替えて貯蔵する働きがありますので、脂肪が体に蓄積され、メタボリックシンドロームを引き起こしやすくなります。
◆歯周病菌が作り出す炎症物質による影響
歯周病菌が作り出す炎症物質が脂肪を増やす可能性が高い、ということもマウスを使った実験などで明らかになっています。
その実験では、歯周病菌によって作り出される炎症物質をマウスの体内に入れ、その後に高脂質のエサを与えると、肝臓や脂肪組織に脂肪が蓄積され体重が増加しましたが、炎症物質を与えなかったマウスでは高脂質のエサを与えても体重は増加しませんでした。
また、歯周病によって起こる歯周ポケットが4ミリ以上になると肥満やメタボリックシンドロームを起こしやすいことが4年間にわたって行われた調査でも報告されています。
歯周治療を行うことによって、血中のコレステロール値が減少したという研究もあります。以上のような研究結果から見ても、歯周病が全身にも影響を及ぼし、肥満を誘発している可能性が高いと言えるでしょう。
2-2メタボリックシンドロームの人は歯周病にかかりやすい
メタボリックシンドロームと診断された場合、内臓脂肪の量は多いということになります。内臓脂肪はアディポサイトカインと呼ばれるホルモンの分泌を行っており、血液中の糖質や脂質、血圧を良い状態に保つ役割をしていますが、肥満が進行して内臓脂肪が肥大すると分泌に異変が起こるようになり、体に悪い働きをするようになります。
その結果血糖値を調整するインシュリンの働きが悪くなって血糖値が下がりにくくなる、というようなことが起こります。
血糖値が上がったままだと、血液が全身に栄養や酸素を運ぶ力が低下してしまい、免疫力が低下していきます。
歯周病は歯周病菌の感染による細菌感染症ですので、免疫が低下することによってリスクが高まり、歯周病にかかりやすく、また悪化しやすくなってしまいます。
3.メタボリックドミノについて

3-1メタボリックドミノとは
「メタボリックドミノ」という言葉があります。
これは、生活習慣病がまるでドミノ倒しのように一気に進み、最後には命にかかわるような様々な病気を引き起こしていく状態を言います。
メタボリックドミノの最初に来るのは、肥満、特に内臓脂肪型の肥満です。脂肪細胞には、余分なエネルギーを脂肪として蓄積する役目のほかに、様々なホルモンを分泌する役目もあります。
健康な状態であれば、小さな脂肪細胞から良いホルモンが分泌され体を守る役割をしますが、脂肪細胞が肥大化すると体に悪い働きをするホルモンが分泌されるようになり、血圧を上げたり、血栓をできやすくしたり、インシュリン抵抗性を上げたりなど、生活習慣病を次々に起こしやすくしてしまいます。
3-2メタボリックドミノの本当の第一歩が歯周病ということも!?
一般的にはメタボリックドミノの最初の一枚目は肥満と言われますが、実はその肥満を引き起こしやすくする歯周病は、肥満よりもさらに上流に位置しているとも言えます。
マウスを使った実験で、歯周病菌が出す炎症物質をマウスの体内に入れると脂肪が増加した、という結果から見て歯周病が肥満の原因である可能性は高いと言えますし、また、歯周病菌は炎症を起こした歯茎の出血部分から血管に入りこんで全身へと流れ、さまざまな作用をすることがわかっているからです。
4.メタボリックシンドロームを改善・予防するためにできること
メタボリックシンドロームを改善、または予防するためには、
「肥満にならないように食事内容や食事の量に気を付けて、栄養バランスの取れた食生活を送る」
「運動不足にならないように毎日適度な運動を心がける」
といったことはもちろん基本的なこととして大事になります。
ですが、メタボリックドミノの真の第一段階ともなりうる歯周病のドミノを倒さないようにすることにも注意を払うことをおすすめします。
繰り返しにはなりますが、歯周病になると「よく噛めなくなることから糖質過多な食事になりやすくなる」「歯周病菌の影響で脂肪細胞が増えやすくなる」ということがあるからです。
歯周病にならないようにするためには、毎日の歯磨きを丁寧に行うこと、歯茎の炎症を起こしやすくする糖質を摂りすぎないようにすること、定期的に歯科でクリーニングをうけること、といったことを実践していくとよいでしょう。
5.まとめ
人はだれしも年齢を重ねるとともに新陳代謝が落ちてしまいますので、食べ物の豊富な時代に生きている私たちは、中年以降、誰しもメタボリックシンドロームになるリスクがあります。
メタボリックシンドロームは放置すると、命に係わるさまざまな重大疾患の原因になるため、もしそのような診断を受けたら早急に改善が必要です。
その場合、不適切な食事や運動不足の改善は基本的なこととして重要となりますが、肥満を招きやすくなる歯周病にかからないようにするということも大事です。
メタボリックシンドロームを予防したい、改善したい、という方はぜひお口の健康にも最大限に注意を払ってみてください。
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!